2025.08.28

美容整形と法律の基礎知識:安心して施術を受けるために知っておきたい10のポイント
この記事がオススメな方
-
美容整形をこれから初めて検討する20代女性
施術に関する基礎知識だけでなく、契約や年齢制限といった法律面の不安を抱えている層に対し、安心材料となる情報を提供できます。
-
未成年の娘の美容整形を相談されている保護者
未成年施術に必要な法的手続きや親の役割を知ることで、正しい判断と適切な対応ができるようになります。
-
美容クリニックとのトラブルに直面している女性
返金対応や医療事故に関する法的基準を知ることで、冷静に自分の状況を整理し、適切な窓口へ相談できるよう導きます。
-
美容医療に関心のあるが慎重な姿勢の30〜40代女性
広告やSNSで情報を集めている段階で、信頼できるクリニックを見極めたいと考えている層に向けた予防知識として有用です。
-
美容整形を職業的に扱うライター・美容メディア関係者
施術だけでなく法律面のリスクと対応策を理解し、記事制作やインタビューでの信頼性向上に活かすことができます。
-
年齢制限と保護者同意の法的ルール
美容整形において未成年が施術を受けるには、保護者の同意が法的に必要であり、実際に同伴を求められることもあります。改正民法により成人年齢が18歳となったことで、18~19歳も原則は自己判断が可能ですが、クリニックによってはリスク回避の観点から親の同意を求めるケースもあります。正しい年齢要件を理解しておくことで、トラブルを未然に防げます。
-
医師の説明義務と契約時の注意点
美容整形は医療行為であり、施術前に医師から十分な説明(インフォームドコンセント)を受けたうえで契約する必要があります。判例でも説明不足による医師の責任が認められた事例があり、書面での同意取得や契約条件の明示が重要とされています。契約時にはキャンセル規定や施術内容の変更可否も確認すべきです。
-
クーリングオフ制度の適用可否
医療契約は原則としてクーリングオフの対象外ですが、自由診療かつ特定商取引法に該当する場合には適用の可能性があります。施術がエステや物販とセットになっているケースでは、法律の枠組みが変わることがあるため、消費者契約法や商取引法の保護対象となる場合もあります。契約書の性質を正確に理解することが肝要です。
-
トラブル発生時の返金・損害賠償請求の基準
結果に不満があっても返金が認められるのは、医師の過失が立証された場合に限られます。具体的には、標準医療を逸脱していたり、説明義務が果たされていなかった場合に民事上の責任が問われます。損害賠償請求には証拠や診断記録が不可欠であり、事後の対応を正確に把握することが重要です。
-
公的機関の規制と相談窓口
美容医療に関連する広告・表示・販売促進については、厚生労働省や消費者庁が厳格なガイドラインを設けており、違反した場合は指導・是正措置が取られます。消費生活センター(188)や医療安全支援センター、日本医療ADR制度など、信頼できる公的機関のサポートを活用することで、安全な施術環境と適切なトラブル対応が可能になります。
美容整形の年齢制限と保護者同意のルール
美容整形を希望する女性がまず知っておくべき法律上の基本は「年齢制限」です。日本において、医療行為としての美容整形は医師法や医療法に基づき提供されますが、年齢に関しては民法の定めが大きく関わってきます。
具体的には、20歳未満(2022年4月の改正民法により18歳未満)の未成年者が美容整形を受ける場合、親権者(保護者)の同意が法的に必要とされています。これは、医療行為が身体に大きな影響を及ぼす可能性があるため、未成年者の判断力だけで完結させないよう保護する制度です。
クリニックでは同意書の提出が求められるほか、実際に保護者が同行するよう案内されるケースもあります。保護者の同意がなければ、たとえ本人が希望していても施術は行えません。また、同意書があっても、一部の施術(豊胸術・鼻形成など)については年齢的リスクを理由に断られることもあります。

契約と説明義務:インフォームドコンセントの重要性
美容整形では、医療契約における「説明義務」――すなわちインフォームドコンセントが極めて重要です。これは医師が施術内容やリスク、副作用、術後の経過などを患者に十分説明し、理解・納得のうえで同意を得るプロセスを指します。
2001年、最高裁が下した判例(最高裁平成13年11月27日判決)でも、インフォームドコンセントの不十分さが医師の説明義務違反とされ、高額な損害賠償が認められました。このような判例からも明らかなように、医師側には詳細な説明と記録を残す義務が法的に課されています。
消費者としては、口頭説明だけでなく、書面での施術同意書の控えを必ず受け取ること、不明点は遠慮せず確認する姿勢が必要です。また、契約時に「施術の変更・中止が可能か」「キャンセルポリシーはどうなっているか」なども確認しておくと、トラブル回避に繋がります。
クーリングオフ制度とその適用範囲
美容整形を巡る消費者トラブルで多く挙げられるのが「クーリングオフ制度」の誤解です。特定商取引法により、一定条件下での契約には8日以内であれば無条件で契約解除できる制度が設けられていますが、医療契約全般は原則としてクーリングオフ制度の対象外です。
ただし例外的に、自由診療で高額の契約が結ばれた場合や、エステティック契約と一体で行われた場合などには、「特定継続的役務提供」に該当する可能性があります。2017年には国民生活センターがこの点について注意喚起を行っており、明確に医療サービスと区別されていない場合は消費者庁が調査を行うこともあります。
つまり、美容医療であっても商取引とされる場合には、消費者契約法や特定商取引法によって保護される可能性があるということです。消費者は「医療契約なのか商業契約なのか」をしっかりと確認する必要があります。
医療事故・失敗に対する法的救済と返金請求の可否
施術の結果に満足できなかった場合、「失敗」や「返金」を求める声があがることがありますが、法的に返金が認められるのは医師に過失があったと客観的に認定された場合に限られます。これは民法上の不法行為責任や債務不履行責任に基づくものです。
医師に過失があると判断されるには、医学的に標準とされる手技を著しく逸脱していたことや、説明義務を怠っていたことなどが証明される必要があります。例えば、2013年の東京地裁の事例では、豊胸術の説明不足が指摘され、約600万円の損害賠償が認定されました。
一方、期待通りの結果が得られなかっただけでは返金は認められないのが通例です。これらのケースでは、日本医療機能評価機構や都道府県の医療安全支援センター、弁護士などに相談することが現実的な対処手段となります。
消費者庁や公的機関が定めるガイドラインと相談窓口
美容整形における広告や勧誘、契約の透明性については、消費者庁や厚生労働省がガイドラインを設けています。特に、虚偽広告や過剰な症例表示、過大な割引表示は「景品表示法」や「医療広告ガイドライン」により禁止されています。
2023年現在、厚労省の「医療広告ガイドライン」に基づき、症例写真を用いた広告には術前・術後の明確な記載や個人差があることの明記が義務づけられています。また、未承認医療機器の表示や「絶対に安全」などの表現も厳しく制限されています。
トラブルや不安を感じた場合は、全国の消費生活センター(消費者ホットライン:188)や、日本医療安全調査機構の医療ADR(裁判外紛争解決)制度などの相談窓口を活用することが推奨されます。
まとめ
美容整形を安心して受けるためには、年齢制限や保護者同意の有無、医師による十分な説明(インフォームドコンセント)、契約内容の確認、クーリングオフ制度の適用範囲、トラブル発生時の返金・損害賠償の基準、そして広告や勧誘に関する法的ルールなど、複数の法律知識を正しく理解しておくことが重要です。これらのポイントを押さえることで、施術前後の不安やトラブルを防ぎ、納得のいく美容医療を選択することが可能になります。
ライター
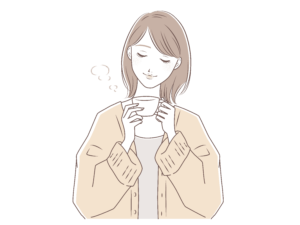
- 彩香 (Ayaka)
- 35歳
-
- 彩香 (Ayaka)
- 35歳
- 経歴
- 大学で美容学とジャーナリズムを専攻し、美容業界でのキャリアをスタート。卒業後、美容クリニックで数年間働き、医療脱毛や美容整形の施術に関する深い知識と実務経験を積む。 その後、美容関連の雑誌やウェブサイトでライターとして活動を開始し、現在はフリーランスとして活動中。
- 専門分野
- 美容整形(フェイスリフト、鼻整形、豊胸手術など)
- 美容皮膚科(医療脱毛、スキンケア治療、リジュビネーションなど)
- 健康と美容に関するトレンド
- 美容製品と化粧品レビュー
- 趣味
- 新しい美容製品や施術を試すこと
- 美容に関するセミナーやイベントに参加
- ヨガやフィットネスで健康を維持
- 美容ブログやSNSで最新情報を発信





